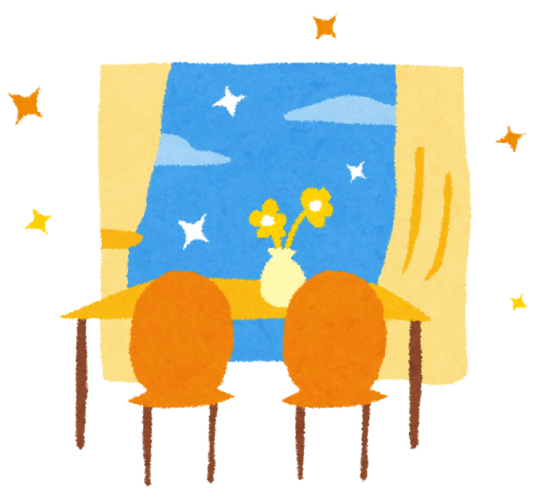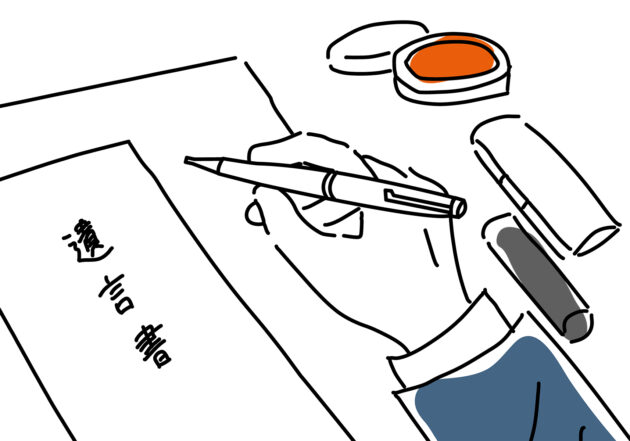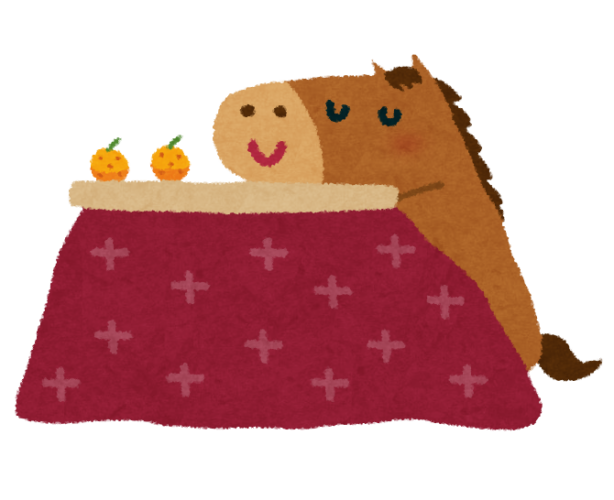家庭裁判所における自筆証書遺言の検認手続きとは
被相続人の亡き後、自筆証書遺言が出てきた場合には、どのような法的ルールのもと、何をどのようにすべきか、また、その効果はどのようなものなのか、生涯に幾度も経験することではない為、知らない方が殆どです。
今回は、自筆証書遺言につて法的ルールや手続きなどの全体像を分かりやすく解説します。

●自筆証書遺言を発見した者は
未開封のまま遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てをする必要があります。申立てを怠ったり、開封した場合には5万円の過料に処されるので注意して下さい。
●申立てに必要な手続きは
・遺言書
・被相続人の出生から死亡時までの全戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
※被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は、被相続人だけではなく、その両親の出生からの戸籍謄本と兄弟姉妹、甥姪の出生からの戸籍謄本が必要となる為、戸籍を集めるのに時間がかかります。
●申立て~家庭裁判所の対応 ※検認手続きは通常1~2ヶ月程
申立てをすると、家庭裁判所から申立人及び相続人に「〇月〇日〇時から〇〇家庭裁判所において検認手続きを行います」という通知が届きます。
検認日は平日です。自分が行けない場合には代理人を立てることも可能ですが、代理人を立てず出席すらしない場合(全員が集まらない)でも検認には影響はなく、指定日に検認が開始されます。※欠席者には後日通知
裁判所では、遺言書を開封し「紙質、利用筆記用具、内容、印影、作成日等」を全員で確認し、保管者や発見者から事情聴取、出席者から筆跡や印影等について意見聴取を行った後に、検認調書を作成します。
【検認手続きの効果】
検認は遺言書の現状保存(検証 証拠保全)手続きであり、後日の偽造、変造を防ぐ目的のため、遺言の法的な有効・無効を判断する手続きではないことに留意して下さい。
検認証明の発行後に始めて、預貯金の解約や不動産の名義変更ができる事になる為、検認手続きが終了してない自筆証書遺言は、相続手続きには使えないことになります。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
上記のルールを知らずに遺言書を開封し、自分に不都合な内容の遺言書だった場合などに遺言書を隠蔽、破棄するようなトラブルも現場実務では起こっております。
このような不正を防ぎ、親族間での遺産分けを公平に行いトラブルを防ぐ方法など、不安に感じた方は下記、メルマガ登録の無料相談からお気軽にご相談下さい。 相談は全国Zoomで対応しております。 2026. 1. 12
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。