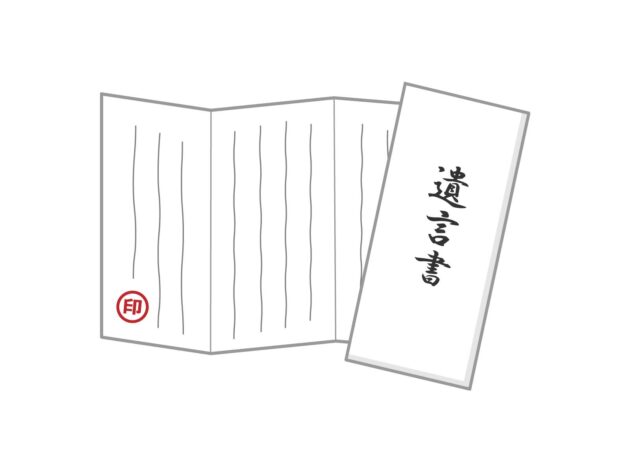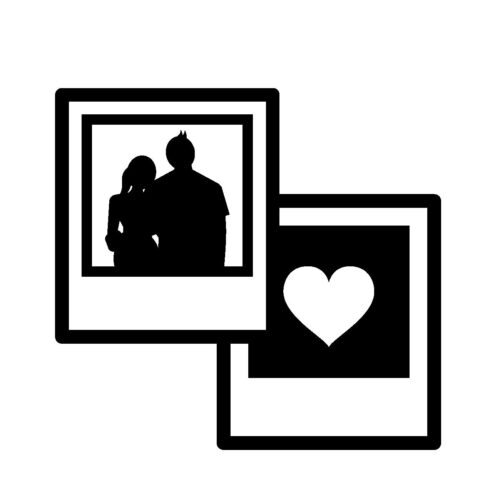防犯対策 その2
近頃、連続強盗事件や空き巣など、凶悪な事件が多く、身近に感じ、住まいの防犯対策を見直す方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸マンションのオーナーが、自分の所有するマンションがもしかしたら狙われやすい条件に当てはまるかもしれない、とわかったらどのような対策をすればよいのかを考えてみましょう。
◆どのような防犯対策が効果的か
①防犯カメラの設置・・・エントランス・エレベーター・駐輪場・ゴミ置き場など
防犯カメラは、
・犯罪の抑止効果
・入居者の安心感
・証拠を残せる
などの効果があり、共同住宅ではとても重要な設備となります。
「防犯カメラ作動中」のステッカーを貼るのも効果的です。
②共有部分の照明強化・・・共有廊下・エントランス・駐輪場など
人感センサー付きのLEDライトを取り付けるのが良いでしょう
もし、建物周辺の街灯が不足している場合は、市区町村などに問い合わせて増設してもらえるようにお願いしてみましょう
③玄関や窓の防犯強化・・・防犯性の高い鍵・補助錠・防犯フィルムなど
侵入に時間がかかるような対策が効果的と言われています。
④オートロックと宅配ボックスの導入
宅配ボックスは、住人が他人と対面する機会を減らすことで防犯に繋がります。
⑤居住者の防犯意識を向上させる
・「防犯マニュアル」を配布する
・掲示板に不審者情報などを掲載する
・オートロックの共連れ注意を呼びかける

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
いかがだったでしょうか。
すぐには全部できなくても、犯罪リスクを少しでも減らすためにすぐできることからやってみてはいかがでしょうか。2025.11.15
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。