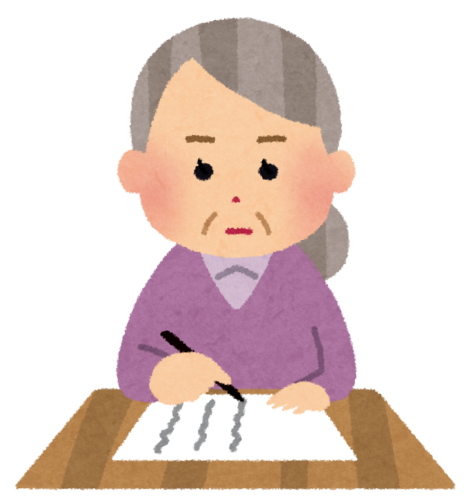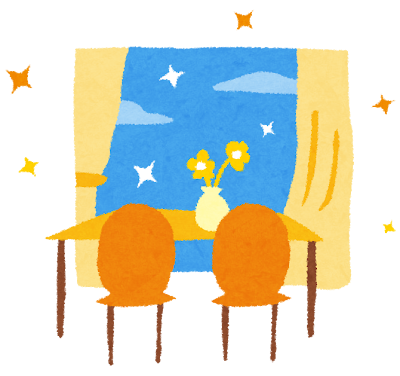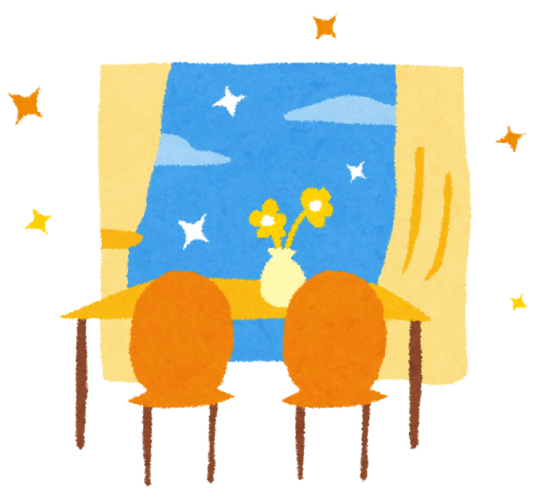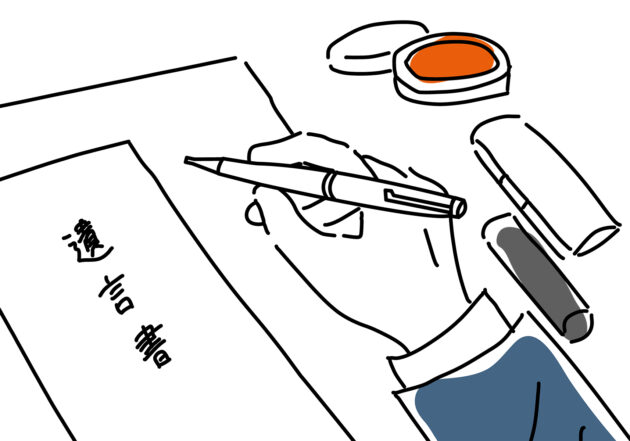不動産・相続に関する令和8年度の税制改正大綱の要約留意点と対抗策
令和8年度の税制改正大綱(令和7年12月26日 閣議決定)全121ページから、不動産や相続関連に的を絞り、解り易く要約してお伝えすると共に、改正に対する対抗策も含めた全容と見て行きましょう。
尚、現時点では改正案のため、今後、国会等で多少変更される可能性があることを承知おき下さい。

■改正1 賃貸収益不動産の5年ルール
賃貸収益不動産(賃貸アパートやマンション)は、相続対策として資産家の方にとっては節税圧縮効果が高い常套手段です。しかし、今回の改正で「相続開始前5年以内に取得した賃貸不動産」は通常の価格で評価すると明記されました。
通常の価格とは時価のことです。(実際の時価目安は取得価格の8割程度)
■改正2 小口化不動産は全て時価評価とする
こちらは前記の賃貸不動産より更に厳しく、「取得時期に関わらず時価評価」と記載があります。また、既に保有中の小口化不動産商品に関しても、改正後に相続や贈与が発生すれば全て時価評価になります!
●改正に伴う市場の変化は・・
今後、改正内容から推察できることは、小口化不動産商品を保有していた相続対策者は、小口化商品を手放し、通常の賃貸不動産に資産を組み替えることが予測されます。
この流れから需要と供給のバランスを考えれば、通常の賃貸不動産(アパート、マンション等)の購入者が増え(需要増)、物件数が減る(供給減)となり、必然的に賃貸不動産の価格が高騰することになります。
●改正の対抗策とは・・
対抗策1 所有地に建築する
改正大綱には例外規定がり、その内容は「通達に定める日までに、5年以上前から所有している土地に新築した家屋(建築中含む)には適用しない」とあります。
つまり、土地建物全てに対して5年 時価評価ルールの対象外になるわけです。従い、新規購入ではなく既存の土地を活かすことで、今までの圧縮効果が享受できることになります。
ちなみに、通達に定める日がいつになるかは未定ですが、令和5年の改正大綱(タワマン改正)の時は、翌年の9月に通達がでた経緯があるので、参考にして下さい。
対抗策2 所有する賃貸不動産のリフォームをする
既に所有している賃貸不動産のリフォーム工事等を行うことで、相続財産を減らすことが出来る反面、建物相続評価は上がらず、更には、賃料アップや空室率が改善することで、将来の運用資金の準備が可能です。
対抗策3 法人へ資産を移行する
個人所有の資産を法人に移行することで、今回の改正内容の直撃を回避します。ポイントは法人の株価評価を純資産方式ではなく、類似業種比準方式の適用を目指すことです。純資産方式は不動産の含み益の影響を受けやすいため、類似業種比準方式にすることで、不動産の圧縮効果が期待できます。
対抗策3 本年中に贈与すること
本改正内容が適用されるのは「令和9年度」からです。従い、小口化不動産等を本年度中に贈与することで現行の低い評価額で資産を移転できることになります。
相続時精算課税制度や暦年贈与を上手に組み合わせて贈与を検討してみて下さい。
対抗策4 生命保険の加入を利用する
小口化商品を相続対策だけでなく、資産運用として保有し続ける方にとっては、将来の相続資産が当初より増加することに伴い納税資金の確保も必要です。
そこで、親が子へ贈与した資金を基でに「契約者=子・被保険者=親・受取人=子」の生命保険に加入します。この場合、最終的に生命保険を受け取る子供の税金は「一時所得」になり子供が支払う納税資金を準備することができます。
対抗策5 小口化不動産の組換えをする
時価評価となる小口化不動産を売却し、通常の賃貸不動産に組み替えることで、5年以上長生きすれば、不動産評価圧縮効果を得ることができます。
また、組換え資産は不動産に限らず、生命保険にすることで生命保険加入時点から相続時に非課税枠「500万円×法定相続人数」による資産の圧縮効果があります。
生命保険を活用する際は、保険金が相続税の対象になる契約方法や終身保険、外貨建ての同時運用など、幾つかのポイントがあるため、専門家に相談しながら加入しましょう!
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
今回お伝えした対策をするにしても、大事なのは現状分析です。現在と将来に向け、自身がどのような状態なのかを分析してから各種対策をしないと、鏡を見ないで化粧をする結果となります。
医者でも事前問診表を記載し、診断、検査を行ったあとに適切な治療を選択し、施術や薬を処方するのと同じです。
弊社では現状分析から施術や処方までを俯瞰的立場からサポートするため、日々学び、実践を繰り返しておりますので、少しでも不安に感じた方は、無料相談からご活用下さい。 2026. 2.21
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。